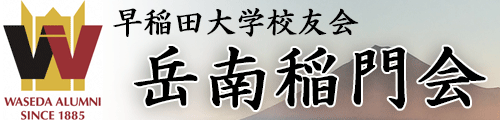出陣する学生の餞に試合を熱望
ひたひたと押し寄せる戦時色。昭和10年代後半の東京六大学野球は、さながら敵国アメリカ生まれの野球に対して弾圧の姿勢を強める軍部への抵抗の時代でもあった。そして、この不幸な時代における野球関係者の情熱の結晶が、太平洋戦争での戦局が悪化した昭和18年(1943年)10月16日、秋晴れの戸塚球場で行われた出陣学徒壮行早慶戦だった。
この1戦が実現するまでには、さまざまな曲折があった。昭和18年といえば、すでに日本を取り巻く戦況は抜き差しならない局面にまで追い込まれていた。それに比例して、敵性スポーツである野球への圧力もエスカレート。海軍内部で行われていたラグビーやサッカーヘの干渉は手控えられたものの、とりわけ軍部に関係のない野球は権力側の格好の標的となったのだった。
具体的には、文部省による中等学校以下への野球禁止令、東京六大学野球へのリーグ解散令である。各大学が野球を続けるかどうかは、それぞれ総長の裁量に任せるとされはしたが、試合などはもってのほか。ただただ1億火の玉の名のもとに、有無を言わせぬ高圧的な指令だった。加えて文科系学生の徴兵延期停止令が出され、12月10日には陸海軍ともに学徒出陣が始まる。およそ世情は野球どころではなかったのである。
思えば、日本の野球史にとってこれほどの暗黒時代はなかったろう。ところが、この状況下にあつて、権力側の意向に逆らう形で早慶戦が敢然と挙行される。日本野球史上での画期的、かつ感動的な一戦。早慶両校の野球を愛する人々の身を賭した奔走が、この試合を実現させたのだった。
××
それは名案だ。出陣する学生諸君の餞(はなむけ)には、確かに全学が一つになれる野球が一番いい。ぜひともやろうじゃないか
慶応野球部長・平井新の進言に、塾長の小泉信三は即座に賛成した。秋に入って学徒出陣が目と鼻の先に迫り、野球部員たちは学窓最後の思い出にと、ライバル早稲田との1戦を熱望。これを受けた平井が小泉に甲し出たものだが、この快諾によって出陣学徒壮行早慶戦は実現に大きく動き出した。
さっそく慶応側は、平井部長のほか、主将の阪昇盛一、マネジャーの片桐潤三の3人が早稲田に出向き、初代監督でリーグ理事の飛田穂洲、野球部長の外岡茂十郎に趣旨を説明。思いがけない申し出に喜ぶ早稲田側と勝敗は問う処に非ず。球場は両校の全学生が集まり得る神宮球場とまで取り決めた。
のイベント。野球を目の敵とする軍部の意向にあえてそむき、学生の意を第一義とする小泉塾長の決断は、緊迫の度を増す戦時下における大英断であり、野球愛好者の枠を超えて歓迎されるべきものだった。
しかし早慶野球部、とりわけ早稲田野球部にとっての苦難の道は、まさにこれが始まりだった。
発案者であり、早慶戦実現に積極的な慶応とは対照的に、軍部・文部省の顔色をうかがうことに汲々としていた早稲田当局がこの時局に野球などとはと、頑(かたく)ななまでに試合実現に立ちふさがったためだ。苦慮する飛田や外岡。
だが、そんな早稲田にも試合実現への功労者が出現する。
マネジャーの相田暢一がその人。そして相田は、この早慶戦だけでな.く、戦後すぐの野球復活において、MVPとでも言うべきクリーンヒットを放つのである。