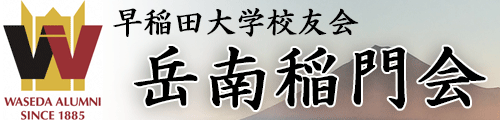一身賭し早大総長に直談判
相田暢一が北海道の小樽中から早稲田野球部に入部したのは、昭和15年(1940年)の春だった。大正期の早稲田で強肩強打の名捕手として名をはせ、卒業後は函館オーシャンでプレーし、都市対抗野球の久慈賞にその名を残す久慈次郎に、中学時代に投球を受けてもらったのが自慢の細身の投手。折しも皇紀二千六百年。各地で奉祝行事が行われ、それとともに野球への圧力が日ごとに増していった時期でもあった。相田は3年の秋からマネジャー業に専念するのだが、色濃くなる一方の軍国色のもと、その学生生活はまさに野球弾圧の真っただ中にあった。
入学早々の昭和15年春のリーグ戦は、文部省の指令でウイークデーの試合が禁止された。1勝1敗の場合、決着をつける第3戦がないのである。開幕日は各校選手が明治神宮を参拝した後に、海軍軍楽隊を先頭に入場行進するものものしさ。結局、リーグ戦は慶応、明治、立教が7勝3敗で並んだが、文部省の意向で優勝決定戦は行われず、3校優勝預かりのままで打ち切られた。圧力はさらにエスカレートし、秋は各校が一度対戦するだけの味気ないものとなる。こうした高圧的な措置は、おもに野球に対してとられたのだが、何せ相手は軍部とタッグを組む文部省。野球関係者は無念さを押し殺し、黙って従うしかなかったのである。むろん相田もその一人だった。
いや、正確には敢然と権力に刃向かった人物もいる。例えば、大正期に慶応の工ースとして活躍した小野三千麿である。3校優勝預かりに終わった昭和15年春季リーグの総評として、小野は毎日新聞紙上で以下のように述べている。
リーグ戦は決勝戦を挙行し、あくまで黒白を決せしめ学生競技の華となっていた。それが決勝戦などするから試合が多くなり過ぎるとか、他のスポーツは週日(平日)に挙行しても差支えないのに、野球だけは罷りならぬとかぢりぢりいじめつけ、遂に今春のように優柔不断な結果となったが、文部当局はこれを見て快哉を叫んでいよう。なぜ快哉を叫んだかといえば、いじめつけが見事成功したからである
××
しかし、こうした野球人の叫びも、権力側にはカエルのツラに何とやらで、痛くもかゆくもなかったようだ。16年12月8日のハワイ真珠湾攻撃によって開戦した太平洋戦争を契機に、野球白眼視の度は増し、職業野球の選乎たちが戦闘帽をかぶって、ストライクをよし、一本!などと言い換えてプレーさせられたのもこのころである。
そして18年に入るや、東京六大学野球にリーグ解散令が出され、12月10日にはついに学徒出陣である。バットやボールを捨て、銃を手に戦地に出向く悲しくも切ない季節の到来だった。こうした状況下で慶応側から持ち込まれた出陣学徒壮行早慶戦に、数々の野球弾圧を忸怩(じくじ)たる思いで耐えてきた相田が、その実現に獅子奮迅の働きを見せたのも当然のことだった。
相田は飛田穂洲や野球部長の外岡茂十郎とともに、軍部や文部省への気兼ねから早慶戦実施に二の足を踏む早稲田当局の説得に奔走する。
総長の田中穂積に直談判する一方で、早稲田を代表する形で慶応との折衝も。
野球部の一マネジャーが総長に直談判するなど、時局を思えば考えられないことだったが、それはそのまま、早慶戦実現にかける相田の身を賭した熱意の表れでもあった。
しかし、それだけで事態が好転するわけもなかった。相田の苦闘はさらに続くのである。